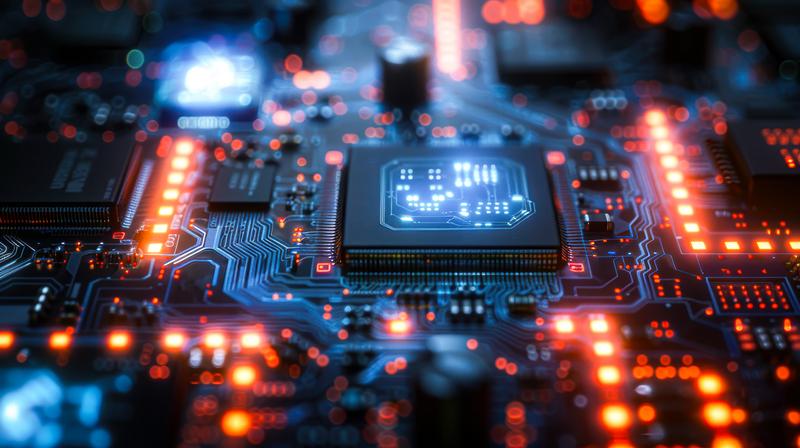皆さん、こんにちは。日本ユニバーサルリハビリテーション協会(ユニリハ)です。
私たちの臨床現場において、日々の支援に欠かせない素材は何でしょうか?車椅子のクッション、療養ベッドのマットレス、義肢装具の緩衝材。その多くに採用されているのが、軽量で弾力性・耐久性に優れる「ポリウレタン」です。
ポリウレタンの機能性は、患者様の姿勢制御や褥瘡予防、快適な生活空間の構築に直結する、まさにリハビリテーション工学の要。しかし、この重要な素材には、環境への課題、すなわち「リサイクルの難しさ」が付きまとっていました。
今回、東京大学の研究チームが、この難題をブレイクスルーする驚くべき技術を開発しました。今回は、リハビリテーションの未来をも変える可能性を秘めた、ポリウレタンの「ケミカルリサイクル」技術について、工学的・科学的な視点を交えて深掘りします。
記事本文:東大による画期的な触媒開発
1. ポリウレタンの特性とリサイクルにおける課題
記事にある通り、ポリウレタンは、その汎用性の高さから、衣類、自動車、そして医療・福祉用具に大量に使われています。化学的には、イソシアネートとポリオールを原料とする高分子化合物(プラスチックの一種)です。
しかし、その分子構造の中にある「ウレタン結合」は非常に安定しており、他のカルボニル化合物に比べて反応性が低いため、熱や水、一般的な化学的手法では、再利用しやすい良質な原料(高級アルコールなど)へ効率良く分解・回収することが困難でした。これまでの分解法では、分解が進みすぎて再利用しにくいメタノールや二酸化炭素になってしまうことが課題でした。これが、ポリウレタンのリサイクルが進まない大きな理由です。

【図1:】 図の挿入指示:プラスチックの原料となるカルボニル化合物の中で、ウレタンが比較的安定した化学構造を持ち、反応性が低いことを示す図 *キャプション案:**図1. カルボニル化合物の反応性の序列。*ポリウレタンのウレタン結合は、他の原料に比べて安定しており分解が困難であることが示されています。(出典:岩﨑孝紀東大准教授提供)
2. 新開発の「イリジウム触媒」がもたらす革新
東京大学大学院工学系研究科の岩﨑孝紀准教授らのチームが開発したのは、この安定したウレタン結合を**「選択的」に分解する、画期的なイリジウム錯体の触媒**です。

【図2:】 図の挿入指示:新しく開発したイリジウムの触媒が、低分子のウレタンを水素化分解し、ホルムアミドとアルコールにする仕組みを示す図 *キャプション案:**図2. 新開発のイリジウム触媒によるウレタン分解のメカニズム。*塩基と水素存在下でウレタンがホルムアミドと高級アルコールに分解されることが示されています。(出典:岩﨑孝紀東大准教授提供)

【図3:】 図の挿入指示:2023年につくったウレアを選択的に分解する触媒(左)と、ウレタンを選択的に分解する触媒(右)の構造比較を示す図 *キャプション案:**図3. ウレア分解触媒(左)とウレタン分解触媒(右)の構造。*触媒の構造を微調整することで、目的のカルボニル化合物を選択的に分解する能力が付与されました。(出典:岩﨑孝紀東大准教授提供)
【技術のポイント】
-
選択的分解の実現: 従来の課題であった「分解しすぎる」ことを避け、ウレタン結合のみをターゲットにして分解します。
-
生成物: 分解後の生成物は、ホルムアミドと高級アルコール。特に高級アルコールは、再び質の高いポリウレタンや他のプラスチックの原料として利用しやすい物質であり、ケミカルリサイクルにおいて非常に価値が高いとされています。
-
実用性の実証: 市販のポリウレタンクッション材を実際に分解できた他、ポリエステルやポリアミドなど、他の樹脂が混ざった混合物からも、ポリウレタンだけを優先的に分解できることが確認されました。
3. 「反応性の序列を触媒で変える」という工学的コンセプト
岩﨑准教授のコメントにある「反応性の序列が決まっているカルボニル化合物において、触媒によって順番を変えることができるというコンセプトは実証できた」という点は、工学的な知見を持つ私たち医療従事者にとって、特に注目すべき点です。
これは、化学反応を意図的に制御し、狙った物質だけを分解する「オーダーメイドの分解」が可能になったことを意味します。リハビリテーション分野で言えば、姿勢や動作の制御を、工学的な構造や物理法則(ニュートン力学など)を応用して実現することと、根本的な考え方は共通しています。
-
ウレア結合や難分解性のイソシアヌレート環(ポリウレタンの耐久性を高める環状構造)といった、これまで分解が難しかった構造にも適用可能であることも、実製品のリサイクルにおいて大きな前進です。

【図4:】 図の挿入指示:新しい触媒を使い、市販のポリウレタンクッション材を液体状のホルムアミドとアルコールに分解できた実験結果の写真を示す図 *キャプション案:**図4. 市販のクッション材の分解実験。*新しい触媒を用いることで、実際に市販されているポリウレタンフォームを液体状の原料に分解できることが確認されました。(出典:岩﨑孝紀東大准教授提供)
リハビリテーション分野への示唆と展望(ユニリハの視点)
このケミカルリサイクル技術は、私たちの臨床現場にどのような影響をもたらすでしょうか。
1. 福祉用具の製造・利用サイクルへの貢献
-
サステナブルな素材の確保: クッションやマットレス、ポジショニングピローなどの主要材料であるポリウレタンを、分解・再合成により循環させることが可能になります。これにより、資源枯渇のリスクが減少し、安定した製品供給につながります。
-
高品質なリサイクルの実現: メタノールになるまで分解されてしまう従来法と異なり、高級アルコールとして回収することで、リサイクル品であっても品質が低下しにくい、高品質な製品への再生が期待されます。
2. 複合素材の利用拡大とリサイクル規制への対応
-
複合製品のリサイクル: 実際の福祉用具や衣類は、ポリウレタンだけでなく、ナイロン、ポリエステル、金属、木材など、複数の素材の組み合わせでできています。この触媒技術は、複合的な廃棄物からポリウレタンのみを抽出的にリサイクルできる可能性を示しており、リサイクルプロセスを大幅に簡素化します。
-
高まる環境規制への対応: 自動車産業をはじめ、世界的にリサイクルに関する規制が強化されています。この技術は、私たち医療・福祉分野が今後、環境負荷の低い、持続可能な製品選択を行う上での大きな追い風となります。

結び
ユニリハは、「医療」と「工学」の知見を融合し、リハビリテーションの質を高める研究を続けています。今回の東大の研究は、まさしく工学と化学の最先端が、私たちの生活と環境、そして医療・福祉の現場を支える素材のサステナビリティに貢献する素晴らしい事例です。
この技術の実用化はまだ途上にありますが、今後の「分解条件の探索」や「触媒の改良」を経て、数年後には私たちの身の回りの福祉用具が、このケミカルリサイクル技術によって生まれ変わる日が来るかもしれません。
ユニリハは、今後もこのような医療と工学を繋ぐ最新情報を、現場の皆様にお届けしてまいります。
【掲載元情報】
-
研究機関: 東京大学大学院工学系研究科
-
研究者: 岩﨑孝紀准教授(有機合成化学)
-
論文掲載誌: 米化学会誌「ジャーナル オブ ザ アメリカン ケミカル ソサエティー」電子版(2024年8月8日付け)